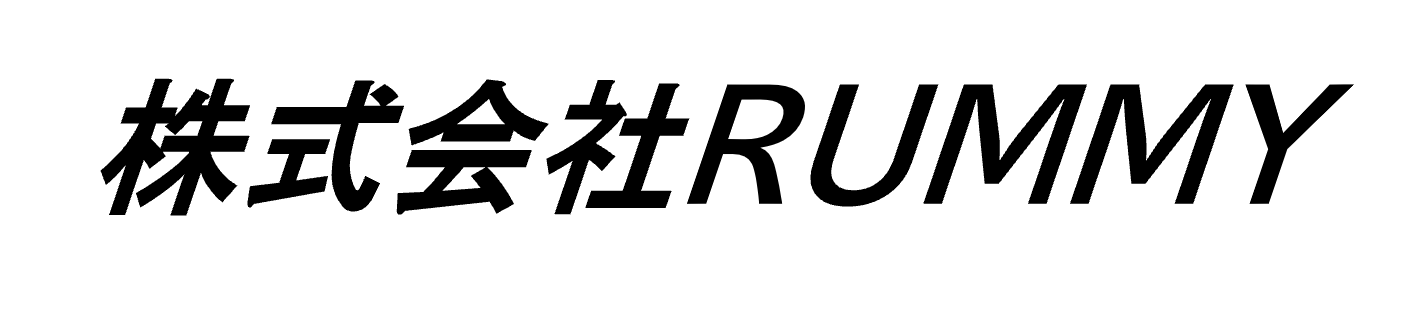― 用語・定義・現象の不整合について ―
はじめに
先日、ある大学教授から「一般の日本語の揺らぎを持ち出すような人が、『半導体光触媒』という分類に異議を唱えるべきではない」という趣旨の言葉をいただいた。
しかし本稿で扱うのは、日本語表現の揺らぎや言葉遣いの好みの問題ではない。
また、特定の研究者や研究分野を否定することを目的としたものでもない。
本稿の主題は、「半導体光触媒」という用語が、現在の物理学・化学の定義に照らして科学的に整合しているのかという、極めて基本的な問いである。

1. 用語は「慣習」ではなく「定義」である
科学技術において、用語は単なるラベルではない。
用語とは、何が起きているのか、何が起きていないのか、どこまでを同一現象として扱うのかを規定する、思考の枠組みそのものである。
したがって、慣習的に使われてきた、分野内で通用しているという理由だけで、用語の妥当性が保証されることはない。
実際、表面化学や材料科学の教育資料には「TiO₂は Eg ≈ 3 eV の真性半導体であり、酸素欠陥によって n 型半導体となる」といった記述がしばしば見られる。
こうした表現は一見もっともらしいが、どの文脈で、どの定義に基づいて「半導体」と呼んでいるのかが曖昧なまま用いられている場合も少なくない。
2. 「半導体」とは何か(定義の確認)
物性物理学において、半導体とは以下の特徴をもつ材料である。
-
明確なバンド構造を有する
-
電子および正孔がキャリアとして定義される
-
電場・電位差・接合構造により、キャリアの移動・分離・回収が議論される
重要なのは、半導体という概念は「電荷輸送と制御」を前提とする材料概念であるという点である。
キャリアの生成・移動・回収を考えない系は、物性物理学的には「半導体」として扱う根拠を失う。
3. 「触媒」とは何か(定義の確認)
一方、触媒とは、化学反応の経路を変化させ活性化エネルギーを低下させるが反応後に自らは消費されない物質である。
触媒の本質は、反応場としてその場に留まり続けることにあり、電子や物質を外部へ取り出し、回収・輸送する主体ではない。
4. 決定的な概念矛盾
ここで、定義上の矛盾が明確になる。
-
半導体:キャリアを生成し、輸送し、回収する概念
-
触媒 :反応場として留まり続ける概念
この二つは、同時には成立しない。
もし電子や正孔が外部に回収されるなら、それは電極反応であり触媒反応ではない。
逆に、触媒として振る舞うなら、キャリア輸送や回収を前提とした半導体モデルは成立しない。
5. 藤嶋–本多効果の正しい位置づけ
1972年に報告された、いわゆる藤嶋–本多効果は、
-
酸化チタン電極
-
対極(白金)
-
電解質溶液
-
外部回路
から構成される光電気化学セルである。
ここで起きているのは、
-
光励起によるキャリア生成
-
電極間の電流
-
電極反応としての水分解
であり、これは光触媒反応ではない。
藤嶋–本多効果は「半導体電極を用いた光電気化学反応」であって、「半導体光触媒反応」ではない。
6. 「半導体」という言葉が用いられるようになった背景
それでは、なぜ「半導体光触媒」という言葉が生まれ、定着したのか。
1970年代以降、固体表面で起こる光誘起反応を理解するために、従来の触媒化学で用いられてきた
「吸着―反応―脱離」
という枠組みだけでは説明が難しい現象が増えていった。
特に酸化チタンのような金属酸化物では、
-
バンドギャップの存在
-
光吸収による電子状態の変化
-
表面で起こる酸化還元反応
が観測され、これらを説明するために半導体物理学の概念体系が援用された。
この段階では、「半導体」という語は
反応機構を説明するための比喩的・モデル的な言語
として用いられていたに過ぎない。
7. モデルが定義にすり替わった問題
しかしその後、本来は説明のためのモデルであったはずの「半導体」という語が、
-
材料の本質的性質
-
反応機構の前提
-
評価法や規格の根拠
として扱われるようになっていった。
その結果、
-
電極構造を持たない系
-
キャリア回収を伴わない系
-
実環境下で局所的に進行する表面反応
に対しても、半導体モデルが自明の前提として適用されるようになった。
ここに、比喩として導入された概念が、定義そのものにすり替わってしまった構造的問題がある。
際に起きている反応の性質
実環境下で酸化チタン表面に起きている現象の多くは、
-
表面準位の形成
-
酸素の吸着と活性化
-
局所的な電子状態の偏り
-
表面で循環する酸化還元反応
によって説明できる。
これは、半導体としてのキャリア輸送現象ではなく、表面化学としての酸化還元反応である。
9. 結論
「半導体光触媒」という言葉は、研究史的・便宜的用語としては理解できる。
しかし、物理学・化学の定義に基づく科学用語としては、内在的な矛盾を含んでいると言わざるを得ない。
用語を正さなければ、評価法は歪み、設計思想は固定化され、実用技術は停滞する。
おわりに
科学において重要なのは、用語を守ることではない。
現象を正しく記述することである。
「半導体光触媒」という言葉を再考することは、過去の研究を否定する行為ではない。
それは、比喩が定義にすり替わった地点を見直し、研究を次の段階へ進めるための不可欠な概念整理である。