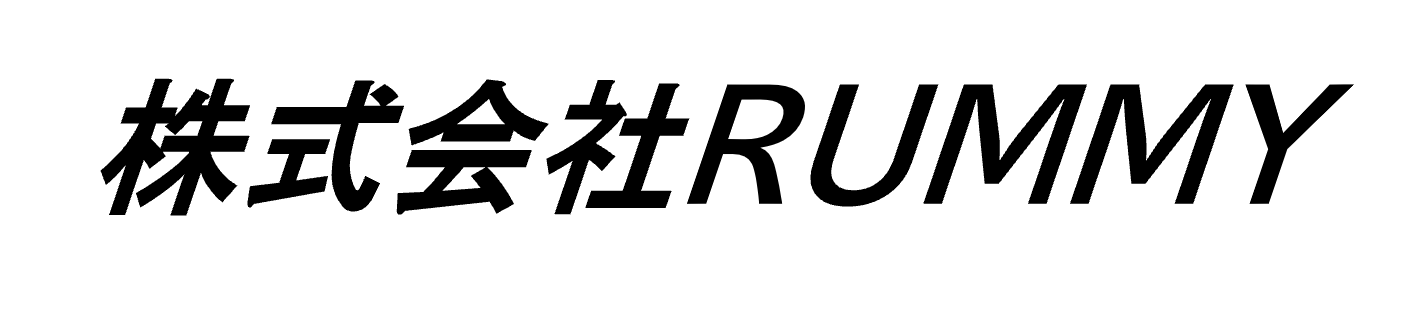ある「比喩」が、光触媒の理解を歪めた ―
1970年代に、酸化チタンを用いた水分解現象が大きな注目を集めました。
この現象は、光・電気・電極・外部回路を組み合わせた光電気化学反応として成立していたものです。
ところがこのとき、研究内容を一般向けに説明するために使われたある象徴的な比喩が、後の光触媒理解に大きな影響を与えました。
その比喩は、
「光が当たると、水が分解される」
「光だけで強い反応が起こる」
という、非常に分かりやすい表現でした。
本来は電極・起電流・助触媒を含む別系統の反応を説明するための比喩でしたが、この説明が独り歩きした結果、光触媒反応、光電気化学反応という本質的に異なる二つの反応が、同一のものとして語られるようになります。
比喩が「前提条件」を消してしまった
この比喩が広まる過程で、次の前提条件が徐々に省略されていきました。
-
外部回路が必要であること、電極反応であること、起電流が関与していること
結果として、
「酸化チタンに光を当てれば、水が分解する」
「光触媒は水がないと反応しない」
という本来成立しない理解が、常識として定着していきます。
ところが、この説明はそれ自体がすでに矛盾を含んでいます。
同じ東京大学の解説資料の中には、「空気中(気相)でもOHラジカルが発生する」という記述が存在しています。
水がなければ反応しないのであれば、空気中でOHラジカルは発生しないはずです。
逆に、空気中でOHラジカルが発生するのであれば、「光触媒は水がなければ反応しない」という説明は成立しません。
この二つを同時に正しいとする論理は存在しません。
これは光触媒現象の問題ではなく、水中実験で成立した反応モデルと、空気中で観測される反応現象を区別せずに同一の説明体系に押し込めてしまった結果です。
つまりここでも、比喩によって前提条件が消され、説明そのものが自己矛盾に陥っているのです。
ここから、水が反応の主役である、ヒドロキシラジカルが中心である、超親水性こそが防汚である
といった説明が主流となり、空気中で起こる酸化反応や、原子状酸素の役割は語られなくなっていきました。
結果として起きた「理解のねじれ」
この比喩を起点として、光触媒の説明は次第に次の方向へ傾いていきます。
空気中反応の軽視、原子状活性酸素の消失、水がなければ反応しないという誤解、強反応・即効性を求める設計思想。
しかし、これは1960年代までに整理されていた本来の光酸化反応の理解とは逆方向でした。
もともと酸化チタン光触媒は、空気中酸素を活性化し、ゆっくりと酸化反応を進めるという性質を持つ技術です。
大量分解や即効性を狙う技術ではありません。
この「比喩」がもたらしたもの
問題は、比喩そのものではありません。
比喩が悪いのではなく、比喩が前提条件を消したことにあります。
その結果、実環境では効かない、期待と現実が一致しない、強く反応させる方向へ無理に設計するという「迷走」が始まりました。
REDOXとの関係について(整理)
本ページで解説しているのは、この比喩を起点として形成された従来型光触媒の理解です。
REDOX(素粒子チタン REDOX ハイブリッド触媒)は、粒子を固定して強反応を起こす、水依存の反応を前提とするといった設計思想を採っていません。
REDOXは、この歴史的な誤解を踏まえたうえで、
強く反応させない
前提条件に依存しない
表面環境を乱さない
という別の方向から設計された非粒子・非膜型の表面環境制御技術です。
一文でまとめるなら
「ある分かりやすい比喩が、光触媒の本質を分かりにくくしてしまった」
REDOXは、その“ねじれ”を理解した上で生まれた技術です。